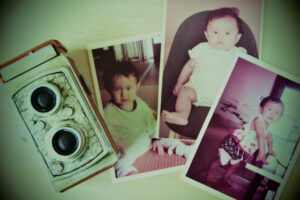複数の認識を同時に抱えることは出来ないんだよねえ
通勤時、ラジオを聴いているが、ある日の番組でパーソナリティが最近読んだ本の話をしてまして、話し方が上手なのか
その本に興味を持ち、すぐに古本屋へ行って、購入、話に引き込まれ一気に読み切ってしまった。
160ページの短編に近い薄い本なのだが、1ページごと話の展開が、コロコロとあっちこっちへ飛ぶ事飛ぶ事。
話に出て来る登場人物も多くなく、基本は男女の電子メールのやりとりなんだが、最初の印象が、これでもかとばかり、
意表を突く告白に、何か嫌な感じ、モヤモヤしたものが残る。最後の文章が結果なのかと思うと、人の見方が変わって
しまうし、見た目や最初の第一印象が、こうも当てにならないのかと痛感する。
本を読み切っても、また違う告白がありそうで怖い。他愛もない事から近寄って、本当の意味を悟らせない文章作りから
お互いの近況の思い違いもあって、言葉を操る人類も、本当は分かっていないのだなと。
後から後から、判明する各々の告白、でも伏線はしっかり回収し、結果整合性が取れている訳で、著者の手法の高さに
感心する。その著者も、覆面作家との事で、これもまた謎が謎を呼ぶのです。また2冊しか発表していないが、もう1冊の
小説も、近未来の生成AIの話で、これもラストのどんでん返しに、また驚かされます。でもあり得るかもなとも
思う訳で、どのジャンルにも属さないであろう分野で、お友達の実話を基にアレンジを加えたとの解説があった。
表題の 「ルビンの壺」は、物事の多様性を理解するプロセスで発生する「大きなハードル」も内包していますね。
ルビンの壺の絵を見る時、人に見えるか、壺に見えるか、これが人も壺も同時に見える事は無いんですね。どちらかにしか
見えないんです。片方の見方をしている時にもう片方の見方は消え失せる。人の認識の特徴でもあります。
よくコンサル何かが言う、「多面的に見る」をしようと思えば、そう容易では無いという事。自分自身の固定化された
モノの見方に対する、変化させる努力を続けなればならないなあと感じます。
人間の脳は、騙されやすいものだ・・・いい方向に騙されるなら良いのだけれど。